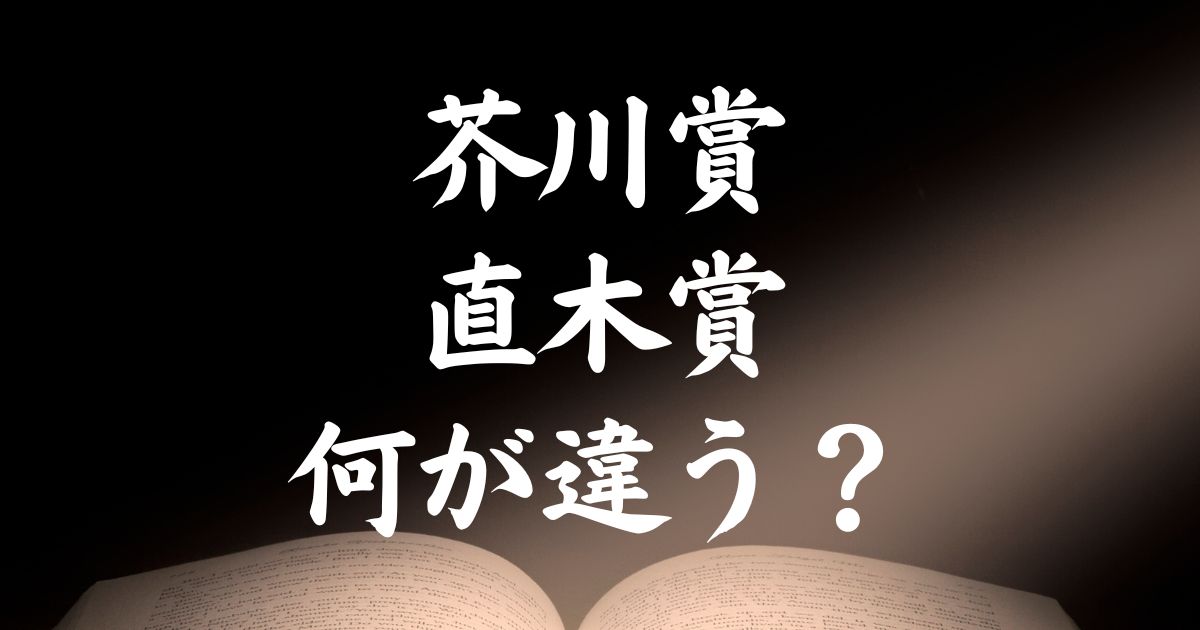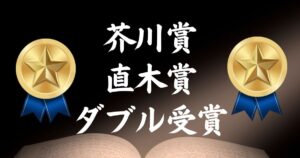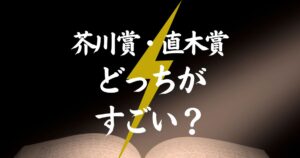「芥川賞と直木賞って、どのような違いがあるんだろう?」
「それぞれの共通点と差異点を知りたい」
と思っている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、芥川賞と直木賞の「5つの違い」と「3つの共通点」を紹介します。
先に結論を表にまとめました↓
| 比較項目 | 芥川賞 | 直木賞 |
|---|---|---|
| 元の人物 | 芥川龍之介 | 直木三十五 |
| ジャンル | 純文学 | 大衆文学 |
| 対象 | 無名・新人作家 | 中堅〜ベテラン (当初は新人作家対象だった) |
| 原稿量 | 短編〜中編 | 短編〜長編 |
| 掲載雑誌 | 文藝春秋 | オール讀物 |
| 創設者 | 菊池寛 | |
| 受賞発表時期 | 毎年1月・7月 | |
| 正賞・副賞 | 正賞:懐中時計 副賞:100万円 | |
記事を読むことで、芥川賞と直木賞の違い・共通点が理解できるようになりますよ。
芥川賞と直木賞の5つの違い
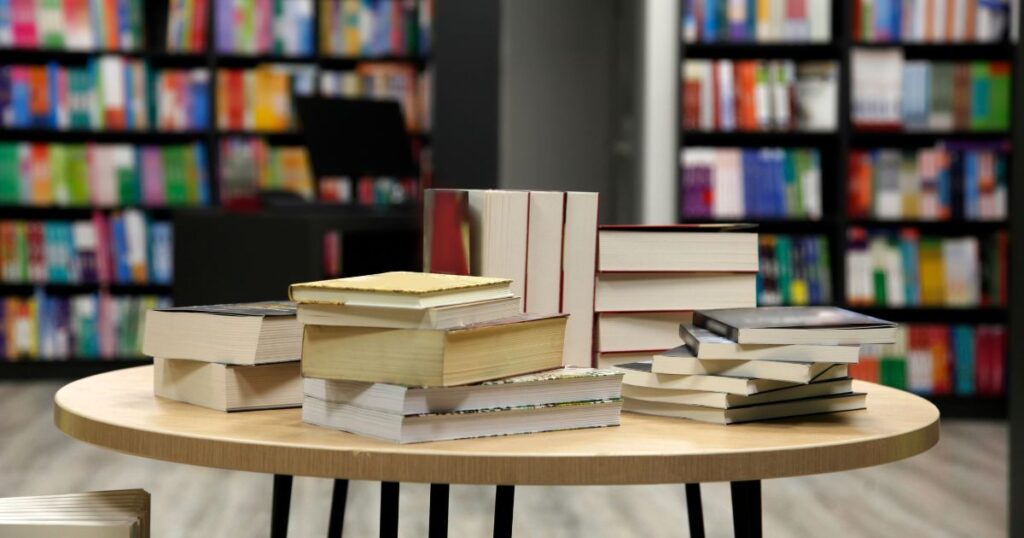
芥川賞と直木賞の違いを解説する前に、日本文学振興会により公式の見解を見ておきましょう↓
芥川賞は、雑誌(同人雑誌を含む)に発表された、新進作家による純文学の中・短編作品のなかから選ばれます。
直木賞は、新進・中堅作家によるエンターテインメント作品の単行本(長編小説もしくは短編集)が対象です。
どうでしょうか。理解できたでしょうか。
まずは、芥川賞と直木賞の5つの違いから解説していきますね。
5つの違いを表にしたものはこちら↓
| 比較項目 | 芥川賞 | 直木賞 |
|---|---|---|
| 元の人物 | 芥川龍之介 | 直木三十五 |
| ジャンル | 純文学 | 大衆文学 |
| 対象 | 無名・新人作家 | 新人・中堅〜ベテラン (当初は新人作家対象だった) |
| 原稿量 | 短編〜中編 | 短編〜長編 |
| 掲載雑誌 | 文藝春秋 | オール讀物 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
違い①:賞の元となった人物
芥川賞と直木賞の違い1つ目は、賞の元となった人物です。
芥川賞のもととなった人物は、芥川龍之介。
明治から大正、昭和初期にかけて活躍した、天才的な作家でした。
代表作には、
- 羅生門
- 鼻
- 蜘蛛の糸
- 地獄変
などがあります。
芥川龍之介は多くの名作を生み出しましたが、35歳という若さで自ら命を絶ってしまいます。
直木賞のもととなった人物は、直木三十五。
大阪出身の個性的な作家でした。
代表作には、
- 南国太平記
- 黄門廻国記(水戸黄門の原作)
などがあります。
直木三十五は、43歳で亡くなりましたが、その功績が称えられて「直木賞」が創設されました。
芥川賞は「芥川龍之介」。直木賞は「直木三十五」。
違い②:「純文学」か「大衆文学(エンタメ)」か
芥川賞と直木賞の違い2つ目は、作品ジャンルです。
芥川賞は「純文学」の小説が対象となります。
純文学というのは、芸術性に重きをおいている作品のこと。
純文学がどのような作品なのかを言い表すのは難しいのですが、特徴としては、
- 文章力や表現力などの芸術性を重視している
- 書き方は「自由」
- 「人生とは?」「今の社会はこのままでいいのか?」などについて掘り下げられることが多い
- 読んだあとの感想は「なるほど…」「うーん、本当にそうなのかな…」「そういう気持ちだったのか」など、自分の思考が揺さぶられることが多い
などが挙げられます。
対して、直木賞は「大衆文学(エンタメ)」の小説が対象となります。
大衆文学の特徴は、
- 内容がわかりやすく面白い
- 「起承転結」などのストーリー性がある
- ミステリー・恋愛・冒険などがテーマになることが多い
- 読んだあとは「あ〜!面白かった!」「感動した…!」「ドキドキした〜」などの感想を持つことが多い。
などが挙げられます。
一般的には、直木賞の方がエンタメ性があるため、受け入れやすい(読みやすい・面白い)と感じる人が多いかもしれませんね。
芥川賞は「純文学」。直木賞は「大衆文学(エンタメ)」。
違い③:対象作家
芥川賞と直木賞の違い3つ目は「対象となる作家」です。
芥川賞は、主に「新人作家」「無名作家」が受賞する傾向にあります。
そのため、芥川賞は「純文学の新人作家の登竜門」と呼ばれることもあります。
一方で、直木賞は主に「中堅作家」〜「ベテラン作家」が受賞する傾向にあります。
(一応「新人」を謳っていますが、中堅作家が取ることが多いです)
かつては、芥川賞と同様「無名・新人作家向けの賞」だったと言われていますが、近年ではその多くが「中堅」〜「ベテラン」の作家が受賞しています。
芥川賞は「無名・新人作家」、直木賞は「中堅・ベテラン作家」のことが多い。
違い④:原稿量
芥川賞と直木賞の違い4つ目は、原稿の量です。
芥川賞は「短編小説」に授与される賞です。
「原稿用紙何枚以内じゃないといけない」という決まりはありませんが、だいたい400字の原稿用紙100〜250枚程度の作品であることが多いです。
(なお芥川賞は、受賞時に単行本として出版されていないこともよくあります)
一方、直木賞は「長編小説」に授与される賞です。
単行本として出版されているものの中から審査が行われるので、芥川賞と比べると原稿量は多いです。
芥川賞は「短編小説」。直木賞は「長編小説」。
違い⑤:掲載雑誌
芥川賞と直木賞の違い5つ目は、掲載される雑誌です。
芥川賞と直木賞を受賞した作品は、その後雑誌に掲載されます。
掲載されるときの「雑誌」と「載り方」が異なるのです。
芥川賞を受賞した作品は、文藝春秋に全文掲載されます。
一方、直木賞を受賞した作品は、オール讀物に一部掲載されます。
毎年、芥川賞・直木賞受賞作品が掲載される「文藝春秋3月号・9月号」「オール讀物2・3月合併号、8・9月合併号」は欠かさず購入してる、という人も多いんですよ。
芥川賞・直木賞が掲載されている文藝春秋&オール讀物の発売日を知りたい方はこちら↓
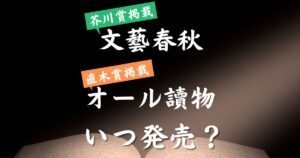
芥川賞は「文藝春秋」、直木賞は「オール讀物」に掲載される
芥川賞と直木賞の3つの共通点

続いて、芥川賞と直木賞の共通点を見ていきましょう。
まずは共通点まとめを表にするとこのようになります↓
| 共通項目 | 内容 |
|---|---|
| 創設者 | 菊池寛 |
| 受賞発表時期 | 毎年1月・7月 |
| 正賞・副賞 | 正賞:懐中時計 副賞:100万円 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
共通点①:創設者
芥川賞・直木賞の共通点1つ目は、同じ創設者によって作られたということ。
実は、芥川賞・直木賞ともに「菊池寛」によって創設されました。
文藝春秋の創設者でもある菊池寛は、亡き友人である芥川龍之介と直木三十五の名を使った文学賞を作ったのです。
芥川賞と直木賞は、菊池寛(文藝春秋の創設者)によって創設された
共通点②:受賞発表時期
芥川賞と直木賞の共通点2つ目は、受賞発表時期です。
芥川賞と直木賞は、毎年2回、7月と1月に発表があります。
- 上半期(7月発表)
→前年12月〜5月までに刊行された雑誌・書籍が対象 - 下半期(1月発表)
→6月〜11月までに刊行された雑誌・書籍が対象
芥川賞と直木賞は同時に発表されるので、毎年2回本屋さんが賑わうきっかけにもなっているんですよ。
芥川賞と直木賞は、毎年2回、7月(上半期)と1月(下半期)に受賞発表がある
共通点③正賞・副賞
芥川賞と直木賞の共通点3つ目は、賞金・副賞が同じことです。
芥川賞と直木賞受賞作家には、正賞と副賞(要は豪華賞品ってことですね)が贈られます。
贈られるものは同じで、
- 正賞:懐中時計
- 副賞:100万円
です。
懐中時計が贈られる理由は、
芥川賞が創設された時代は、生活に苦しむ作家が多くいたため、換金可能で当時高価だった”懐中時計”を正賞とすることに決めた
と、芥川賞・直木賞の創設者である菊池寛が選んだとのことです。
芥川賞と直木賞の正賞・副賞は「懐中時計」と「100万円」
まとめ:芥川賞と直木賞の違いを理解して、自分に合った本を読んでみよう
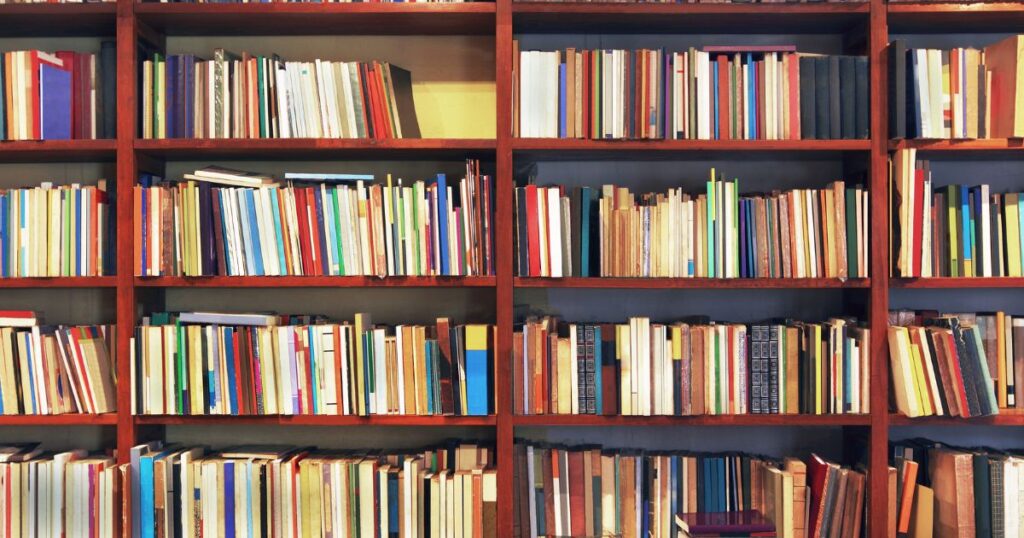
芥川賞と直木賞について紹介してきました。
まとめると、
- 芥川賞と直木賞の5つの違い
- 元となった人物:芥川賞は芥川龍之介、直木賞は直木三十五
- ジャンル:芥川賞は純文学、直木賞は大衆文学(エンターテインメント)
- 対象作家:芥川賞は無名・新人作家、直木賞は新人・中堅〜ベテラン作家
- 原稿量:芥川賞は短編〜中編、直木賞は短編〜長編
- 掲載雑誌:芥川賞は文藝春秋、直木賞はオール讀物
- 芥川賞と直木賞の3つの共通点
- 創設者:どちらも菊池寛(文藝春秋の創設者)によって創設された
- 受賞発表時期:毎年1月(下半期)と7月(上半期)の年2回
- 正賞・副賞:正賞は懐中時計、副賞は100万円
芥川賞と直木賞は「純文学」と「大衆文学」という異なるジャンルを評価する重要な文学賞ですが、同じ創設者によって作られ、同時期に発表される兄弟のような関係にあります。
純文学(芸術性)に触れたい方は「芥川賞」、
エンタメを楽しみたい方は「直木賞」の本を選んでみるといいですね!
歴代の芥川賞受賞作品はこちらでまとめています↓
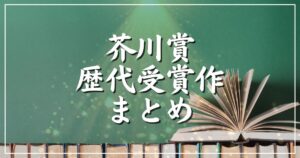
歴代の直木賞受賞作品はこちらでまとめています↓